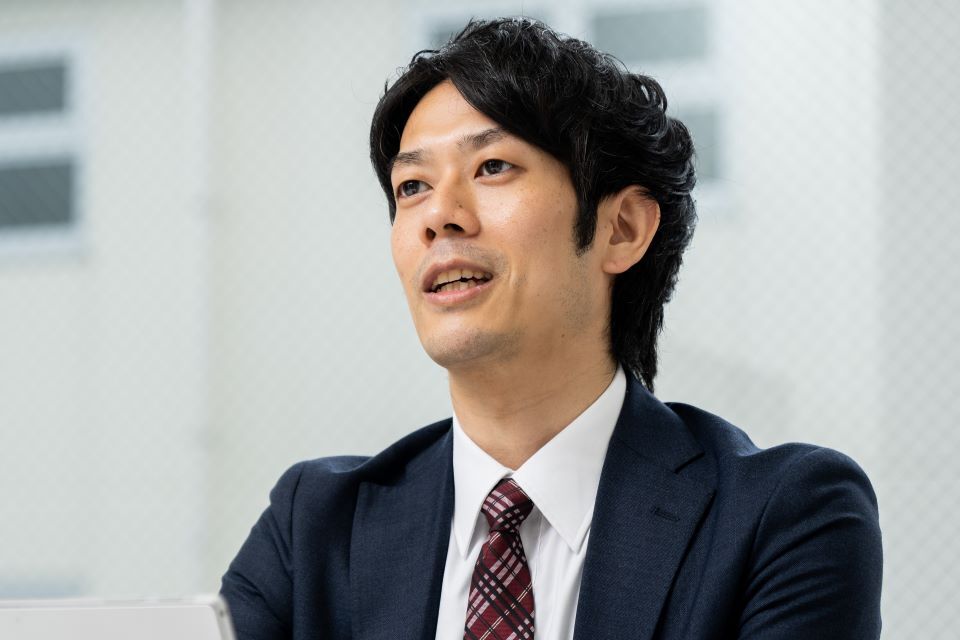N. R. さん
第二事業本部 営業職 中国蘇州駐在 Division Leader
中国東北地区出身。北京師範大学日本語学部日本学科卒業、東京学芸大学修士課程修了後、2006年TSBに入社。東京本社で約3年勤め2009年より蘇州出張所に赴任。プリント基板の法人営業などの業務担当・部長職を務める。
日々の歩みと積み重ねが大きな強みになると実感
異文化を理解し身につける柔軟さも大切
TSB入社以前の経歴は?
中国では北京師範大学で日本語を専攻しており、在学中に日本でホームステイをして、日本が大好きになったんです。そして「卒業後はぜひ日本に行きたい」と、北京師範大学の交流協定校でもある東京学芸大学の修士課程への進学を決め、日本に留学しました。
就職までの経緯は?
東京学芸大学の教授から「博士課程まで進んでほしい」というお話もいただいたのですが、文学で食べていくことには限界を感じる部分があり「ほかの世界も見てみたい」と思いました。そして、中国と関わりのある会社を中心に就職活動をするなかで、出会ったのがTSBです。修士論文を書いている期間からアルバイトとして働かせていただき、修了後正式に入社しました。
TSBを選んだ決め手は?
北京オリンピックのある2008年までには中国に戻りたいと思っていたので、日本での限られた時間を、とにかく内容の濃いものにしようという意思がありました。そう考えるとやはり、中小企業のほうがいろいろなことをさせてもらえるだろう、と。また、募集にあった「世界のステージで羽ばたける」というキャッチフレーズも、自分の思いとマッチしていて惹かれたんですよね。
現在の仕事内容は?
中国華東地区にある蘇州出張所で、営業および現地フォローをおこなう責任者として務めています。商社として、よい商品を安く買ってお客さまに提案して販売する仕事です。日本でスペックインしている商品を工場で製造し納品する、という一連の業務における、営業メンバーへの指示や、品質と納期の管理・指導などもおこなっています。
事業所には何名のメンバーがいますか?
当事業所に業務10名、財務2名、営業8名(うち日本人1名・韓国人1名)、技術15名(うち日本人4名)、同地区内の工場にワーカーと検査員21名が在籍しています。また、営業での外出が多いため、運転手が3名います。
中国で働く面白さはどういった点ですか?
日本では偉い方とのアポはとりにくいものですが、中国では工場やお客さま先でも、トップマネジメント担当者と会える機会が多いんです。キーマンとの関係が構築できると、問題ごとも直接相談できて解決も早い。そのスピード感は、中国ならではの文化ですね。また、中国人は仲間意識が強く、輪のなかに入れてもらえると、思わぬ裏情報が聞けることもあります。それが仕事の有益なヒントになることも多く、中国では人づきあいもひとつの強みになると感じています。
日本とのギャップは感じますか?
中国の人は、物事をストレートに表現するため、日本のような曖昧な言い方だと誤解を招くことがあります。私は赴任当初それが原因で、中国のメンバーの輪に入れない時期がありました。いまでは、要望や指示は簡潔に伝え、壁をつくらず相手と接することで良好な関係を築けています。中国に来て、日本で学んだ思考をそのまま展開しようとするのは、正解ではないんですよね。とはいえ、当社は日本企業なので、日本的な仕事への姿勢は守りつつ、状況に応じて中国の柔軟さを取り入れるとよいのかなと思います。これは、ほかの駐在員にも伝えていることですね。
仕事をするうえで心がけていることは?
自分を知って相手を知ること。やはり仕事をするうえで、人間関係は非常に大きな鍵です。自分の強みと弱みを知ったうえで相手のことを知れば、適切な提案ができますし、よい関係性も構築できます。責任者としては、常に相談しやすくスムーズに問題解決ができる、風通しのよい環境づくりに努めています。私は外出が多く、みんなと顔をあわせる機会が少ないので、コミュニケーションツールWeChatを活用し、困りごとなどがあればいつでも連絡するよう、社員たちに呼びかけています。
TSBではどんな人が歓迎されますか?
ポジティブな思考をもっていて、ある程度辛抱強い人が向いていると思います。仕事に必要な知識や方法、人脈などは、コツコツと積み重ねていくもので、近道はないんですよね。仕事をしていると、トラブルも起きるし、つらいこともたくさんありますが、そのぶん学ぶことも大きい。それを武器にして突き進むことが大切なことなので、くじけずについて来れる人に入ってきて欲しいですね。
求職者へメッセージをお願いします。
人生にはさまざまな選択肢があり、なかでも就職はとても大きな選択となります。家族や先輩、友人たちから助言を得ることもよいですが、就職の答えというものは、必ず自分のなかにあるものです。ですから「自分が本当にしたいことは何か」「自分は何を目指しているのか」に、じっくりと向き合ってください。そして、もしその先に縁があれば、私たちの仲間として、また中国のステージで一緒に羽ばたきましょう!